
元エンジニア志望の高専生が
知的好奇心が導く経営の道
コンサルタント 佐藤 善彦 Sato Yoshihiko
広島県出身。呉高専卒。アメリカの大学にオンラインで通いながらJBAにインターン生として勤務しており、2024年4月から契約社員としてフルタイムで参画。
現在はAI事業本部の中心メンバーとして、大学教授との産学連携での自社AI開発や企画・ライティング業務のAI移行設計、過去のJBA内の情報資産を最大限利活用する情報設計、AI事業本部の主要メンバーとして任されている。
JBAに入ったきっかけ
エンジニアの世界からビジネスへ。人生を変えた東京での1日
幼い頃から自分は「なぜ?」が口癖で、新聞のニュースの意味を親に問いかける毎日でした。その知的好奇心は、小学3年生の時、父から譲り受けたPCでプログラミングと出会ったことで加速し、Javaでアプリケーション開発に挑戦する日々を過ごしました。
高校の進路選択時、最初は県内一の公立校に進学しようとしてましたが、担任から高専を紹介され興味本位で、オープンキャンパスへ。大学生からでなく、高校1年生から専門性を磨けることに魅力を感じ、迷わず高専に進学し、情報工学を専攻。将来はGAFAに就職して、世界トップクラスのエンジニアになることを夢見ていました。
しかし当初は上位だった成績に慢心し、次第に学業への情熱が薄れていきます。就職を検討しましたが、地方の大手メーカーや国立大学の技術職員など、条件の良い就職先はありましたが、自分らしく働ける姿が想像できず、社会を知らないまま"社会人"という見えない道に進むことへの恐怖から、一度進学を決意。しかし動き出しが遅く一般的な国立大学の出願期間を逃してしまい、海外の通信大学に入学。バイトをしながら夜は勉強する生活が続きましたが、フリーターのような暮らしに嫌気がさし、すぐに上京できる長期インターンを探し始めました。
エンジニアとしてのインターンを探す中で出会ったのがJBAでした。面談で「エンジニアのスキルだけを磨いても意味がない」「もっとビジネスを学ばないと、一生使われるだけだよ」と言われ、最初は否定された気がして腹が立ちました。でも、どこかで納得している自分もいました。
その後「インターン生が集まるイベントがあるから参加してみないか」と誘われ、ここで動き始めないと何も変化しないと考え、バイトのシフトを無理やり外し参加を決意しました。初めて訪れる東京のオフィス街に圧倒されながらJBAのオフィスへ向かいました。
そこで初めて目にしたのは、東大生や北大生など、いわゆる高学歴な大学生たちでした。地方から出てきた私にとって、そういった学生たちと直に接するのは初めての経験でした。ビジネスについてのディスカッションを重ねる中で、正直「自分の方が凄いんじゃないか?」と感じました。学歴が無くても関係ない、東京で十分に戦っていけると確信しました。
イベント後、社員に「どうする?」と問われ、「やりたいので上京します」と即答。1週間という短い期間で広島から東京への引っ越しを終え、新しい挑戦への第一歩を踏み出しました。

JBAに入って驚いたこと
トップ大学のインターン生たちと肩を並べ、ビジネスの世界へ踏み出す
入社当初、私はWebの知識を少し持っていたことから、Googleアナリティクスの分析やワイヤーフレームの作成などを担当していました。しかし、ビジネスや企業のことが何も分からず作業的に仕事をする毎日で、特に楽しさを見いだせないままでいました。
そんなある日、マネージャーから突然の連絡が仕事終わりに届きました。「2週間大阪いける?」。詳しい話を聞くと、新しく入社したインターン生を集めて1週間ほど合宿をするとのこと。「佐藤さんも来たらどう?」というマネージャーの誘いに、大阪という新天地への興味と、新しい仲間との出会いへの期待から、即座に承諾しました。
大阪には広島大生数名と、北大生や阪大生もいました。「こいつらも一瞬で抜かしてやる」という闘志を胸に、様々な仕事に取り組みました。誰もが知っている一流企業の採用サイトの提案や企業PRの動画提案など、胸が高鳴る案件に携わることができました。全員でディスカッションしながら、互いの仮説や主張を激しくぶつけ合い、仕事を進めていきました。
2週間が経過し、新たな転機が訪れます。「JBAの採用支援の事業化を学生インターン生でやろう」という話が持ち上がったのです。大阪に滞在する期間を延長することになり、自社の採用活動も担当するようになりました。戦略コンサルに内定した京大生や、数学科の阪大生など、多彩なバックグラウンドを持つ仲間たちと働く中でも、自分は負けていない、という自信は常にありました。
この経験を通じて、ビジネスへの興味が急速に膨らんでいきました。もし自分が経営者になるなら、もっとビジネスを理解する必要がある──その思いが日に日に強くなっていきました。当初は期間を決めていませんでしたが、様々な情報や経験が得られる環境の中で、ここで続ければ広島にいるより断然実力が付くと確信しました。入社して半年と数か月が経ち、2週間の大阪滞在が気づいたら半年経っていた3月頃、「まずはもう一年やろう」という決意を固めました。

JBAの仕事内容
企業を知り尽くすまで突き詰めた先に、確かな手応えがあった
JBAでより多くのプロジェクトを任されるようになったものの、なかなか成果が出せない日々が続きました。特に、お客様との商談では頭の中の質問を言葉にできず、社員から「商談に出た意味あるのか?」と指摘を受けることも。同期は既にお客様と直接やりとりをしたり、プロジェクトを一人で完遂する中、「置いていかれる」という焦りを感じていました。
転機となったのは、ある機械メーカーの企業ブランディングプロジェクトでした。100周年を迎える企業が新たなブランディングを創り上げていくために、まずは社名変更に向けたコンペが開かれました。数社によるコンペで、競合には誰もが知る広告代理店が名を連ねていました。「これで受注できたらすごい。しかも社名を変えるなんて責任重大だ」。そんな思いを胸に抱えながら、最初のキックオフミーティングに社員と共に参加しました。
役員全員が出席するキックオフミーティングでは緊張しましたが、その後の工場見学で、お客様の生の声を聞く機会を得ました。特に印象的だったのは、50年以上第一線で会社を守りながらも、成長させ率いてきた会長の言葉。これまで培ってきた100年間をある意味でぶち壊し、次の100年に向けて企業を変えようとする覚悟に触れ、ビジネスの持つ重みを実感しました。
この経験を機に、お客様のことを徹底的に理解しようと決意。社内報は全て目を通し、Googleの検索結果も50ページ目まで確認しました。技術者主導の上流商流での価値創出、高い納期管理力、企業統合による成長戦略など、企業を深く理解していく過程に夢中になりました。
とことんやり抜きたいという思いから、マネージャーに何度も提案の仮説を相談。資料作成から商談での提案まで全てに携わり、結果として4社コンペの末、受注。
受注してからは社名を決めるための未来の経営幹部を集めたワークショップもマネージャーと二人三脚で実施しました。企業に深く入り込んでプロジェクトを進められることに、大きなやりがいと面白みを感じました。

JBAの成長環境
何でも知れる、何でもできるJBAの環境
JBAが手掛ける企業ブランディングは、企業自身も理解していないような魅力を第三者として正しく理解し、その魅力の全てを効果的に発信する力が求められます。そのためには、企業のあらゆる側面を理解する必要があります。この「企業を知り尽くす」過程に、私は大きな面白さを感じています。
例えば、ある水処理会社の社外広報プロジェクトでは、様々な情報をインプットしていく中で、その企業が持つ技術の奥深さに引き込まれていきました。スケール(水垢)一つを取っても、その種類や化学式、中和の仕組み、センサーによる分析方法など、専門的な知識が必要な分野です。同時に、その企業がどのようなプロセスで規模を拡大していったのか、成長の軌跡もお客様との対話を通じて理解することができました。
また、先ほどの機械メーカーのようなブランディングプロジェクトは、企業のあらゆる側面に関わる全社的なプロジェクトであり、企業経営の全体像を把握できる機会となっています。単なる記念行事の企画ではなく、企業の過去から現在、そして未来へとつながるストーリーを、全社を巻き込んで作り上げていくのです。ある企業では創業期の苦労話から現在の経営判断まで、一貫した価値観で意思決定が行われていることを学びました。また別の企業では、新規事業への挑戦と既存事業の強化という、相反する課題のバランスの取り方を知ることができました。
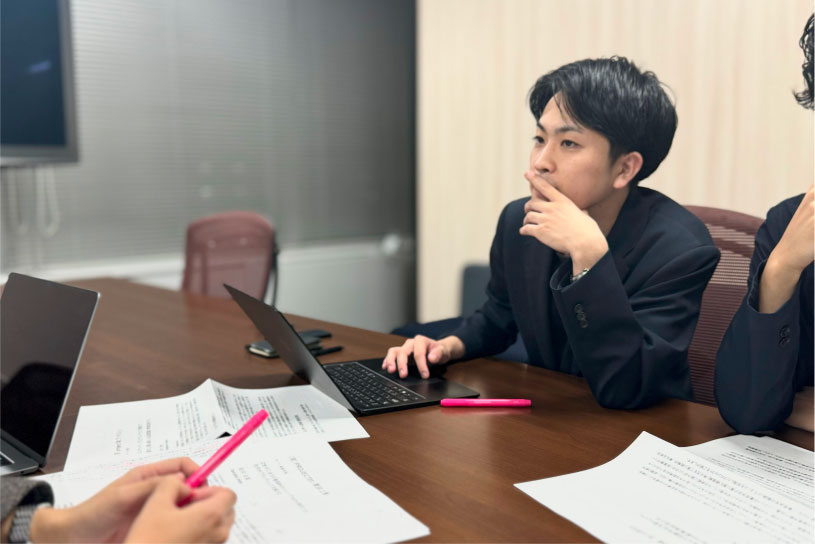
これからのビジョン
目指すは、ビジネスを知り尽くしたエンジニア。
「30歳までに5億円を稼ぐこと」──それが私の目標です。なぜ5億円かというと、純富裕層のボーダーラインが5億円だからです。この金額を稼いで地元で花火大会を開催すること、そして地元の友達を雇えるぐらいの経営者になることが、私の夢です。
エンジニアリング(特にITの技術)への興味は今も変わっていないどころか、むしろ増しています。しかし今は、ビジネスを深く理解したエンジニアになって、経営をしていきたいと考えています。いわゆるフォーブスのトップ企業の創業者たちを見ると、ほとんどがビジネスセンスのあるエンジニアです。例えばイーロンマスク。彼は幼少期、今でいうインベーダーゲームのようなゲームを開発していました。ビル・ゲイツも同様です。このように、エンジニアリングとビジネス、両方の視点を持つことが重要だと確信しています。AIの技術進歩が著しく、アイデアをすぐ形にできてしまう現代において、ビジネスサイドの知識が特に重要であると考えています。
企業の全体像が見えるのも、JBAの大きな魅力です。企業活動の全てを知るためには、経営者になるか、経営コンサルになるか、広報として入り込む以外に方法がありません。広報はマーケティング、営業活動、採用、IR、SRなど、全てのステークホルダーとのコミュニケーションに関わっています。だからこそ全体像が見えるのです。周年事業やAIプロジェクトを通じて様々な業界や企業の動きそのものを理解し、身についていく。これは必ず自分が経営者になったときも活きてくると確信しています。
今の直近の目標は、自分のチームを作ることです。AIも、周年事業も、やりたいことがあまりにたくさんあります。そのためには、自分の2本の手じゃ全く足りません。足も使いたいくらいです。徹底的に企業を理解して、AI等の新たなツールも駆使して、自分と一緒の目的を目指してくれる仲間があと5人いたら、急速に出来ることは増えるのではないかと思っています。
幼い頃からの知的好奇心は今、この明確な目標として結実しています。








